ビジネスをデザインでひらく 公益財団法人大阪産業局・デザイン活用支援 oidc(Osaka Innovative Design Connect)
よくわかる!ブランディング vol.1
ブランディングとマーケティング
こんにちは。
公益財団法人大阪産業局・デザイン活用支援oidcの小山啓一です。
このブログは「企業のブランディング」について、分かりやすくお話していこうという趣旨で書かれています。
...が!
「ブランディングね、うちには関係ない」と笑う事業主さんもいたりして、興味もそれぞれという感じかと思います。
「では、マーケティングはどうですか?」と尋ねると、深く息を吐いて「宣伝広告に使うお金、無いわぁ」と、今度は親指と人差し指で輪を作って、意味深な笑みを頂いたりします。
ただ、知識をインプットしておいて悪いことは無いと思いますので、ぜひこのブログ記事を楽しんで頂きたいです!
「マーケティングって『広告』でしょ?」
「『調査』のことじゃないの?」
「プレゼンしてるイメージあるなぁ」
マーケティングが様々な解釈、理解がされているのには理由があります。
それは、マーケティングが様々なパーツ(構成要素)で成り立っているからなんですね。
調査分析することもマーケティング、広告戦略を作るのもマーケティング、チラシを撒くのも、グーグルに広告を出すのもマーケティングの要素なんですね。
あるカフェオーナーさんに「マーケティングしてますか?」と尋ねると、「早起きして、近隣へのポスティングを頑張ってます。これ、マーケティングですよね」と返事を貰いました。
オーナーさん、間違ってないです!それもマーケティングのひとつのカタチです。もう少し突っ込んでほしいところですが、お店の存在やサービスを知ってもらう努力は本当に重要です。
いろいろな解釈で皆さんが捉えているマーケティングって、いったい何なの?
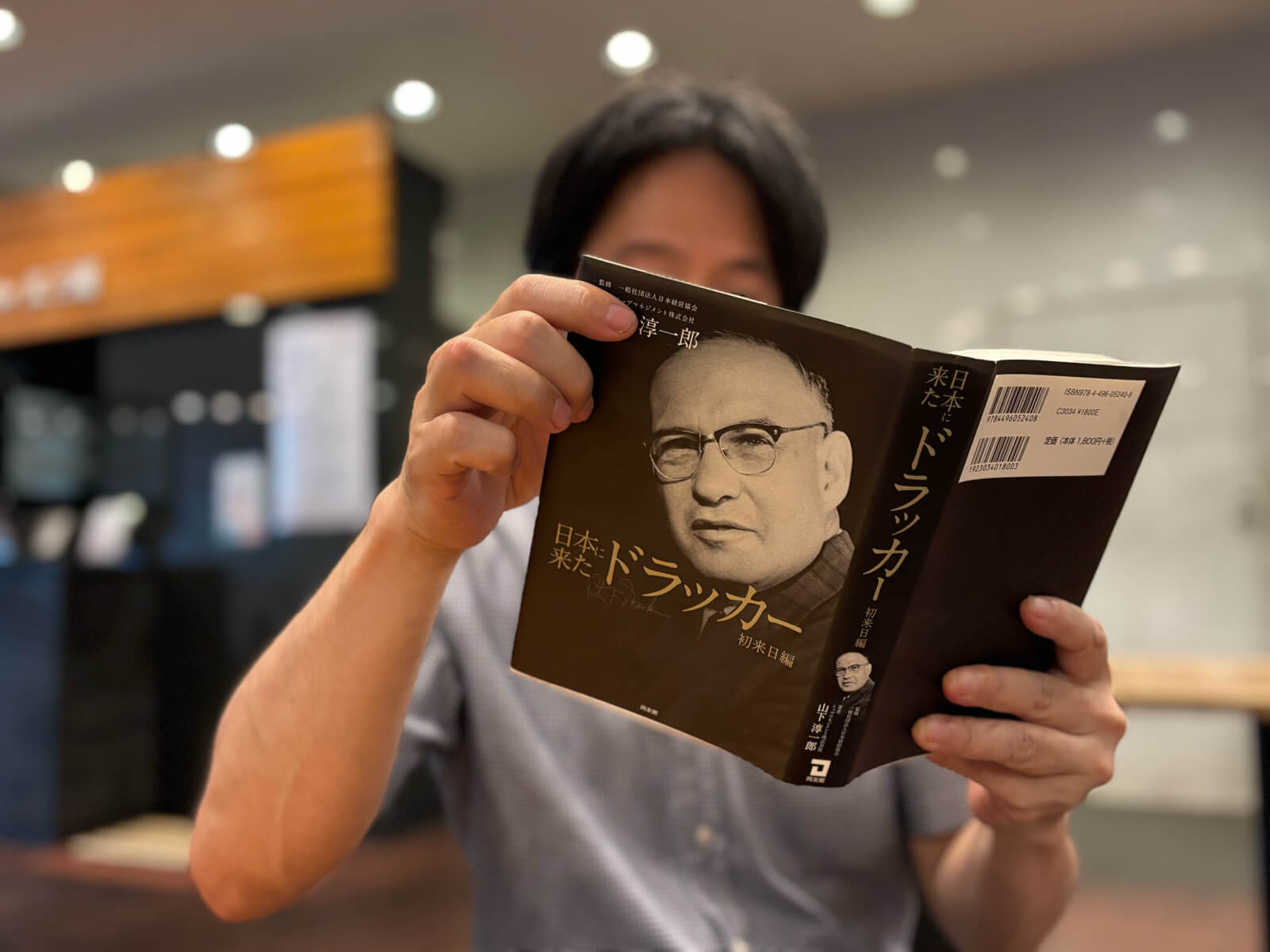
未だに経済学の中心にいる「もしドラ」のドラッカーさん
経営学の権威と言えば「もしドラ」で有名になったピーター・ドラッカーさん。彼はマーケティングについてこう言っています。
「セールス(売る)を無くすものがマーケティングです」と!
「おっと、セールス(売る)を無くすって?売らないということですか?」
いえいえ、ドラッカー先生のこの言葉の解釈としては、「向こうから顧客がやってきて、商品を買っていく」ようにするのがマーケティングだということです。
そして大胆なことに、企業の機能は「マーケティング」と「イノベーション」の二つだと言い切っています。
「え?二つだけ?」と驚きますよね?
御社はいかがですか?マーケティングできてますか?

鴨が葱を背負ってやって来る?
「うちは人気あって、お客も並んでくれてる」と言われる経営者さん。
これ、意識する、しないに関わらず、マーケティングができている状態だといえますね。
素晴らしいです!
「何が勝因なんですか?」
「いやぁ、コーヒーはコンビニより安いし、ランチも500円でお腹いっぱいになれる。そら、並ぶわなぁ」と店長。
「店長、利益出ていますか?」
「まぁ、出ないですよ」
「やっぱり...」
そうなんです!
マーケティング、特にブランディングについては、お客様に “高いお金出しても買って頂ける!” ところがポイントなんですね。
利益を削って、金額ベースでライバル会社と戦うということになると、見ている視点が「ライバル会社」になってしまうんです。
当然、他社分析、もしくはその製品やサービスの調査、分析は重要です。
ただし「相手の半額で商品を出せれば勝てる!」というような価格競争は、いかに安い商品を仕入れるか、利益を削るかに終始してしまいます。
仕入れや原材料等のコストダウンは不可欠ですが、それとマーケティング、ブランディングとは別です。
無理を強いるコストダウン競争は、ライバルを倒産に陥れ、最終的には自滅するという不幸を招きかねないことを歴史が証明しています。
マーケティング・ブランディングにおいて重要なのは「顧客」です。
どこまで行ってもテーマは「人」ですし、「心」や「感情」に根差したものです。
お客さんが向こうからやってきて、高い商品を嬉しそうに買っていく?そんな光景を大阪であれば、御堂筋の高級ブティック街で見かけることができます。30万円のコート、60万円のバッグ、1000万円の腕時計といった具合です。
「高い価格で売れる」というのは置いておいても、「お客さんが向こうからやってきて、買ってくれる」については、「そうなってほしい」と願うのが経営者というものだ…と思うんですが...
どうですか?

マーケティング?ブランディング?
マーケティングという意識を持つことから「ブランディング」はスタートします。
ブランディングが上手くいっているということは、マーケティングができているということになりますね。
ピーター・ドラッカーさんが企業に求めらる機能は「マーケティング」と「イノベーション」だと言っていますから「ブランディング」は「マーケティング」もしくは「イノベーション」に内包されていると考えるのが自然ですね?
マーケティングの目的がセールスを無くすことなので、ブランディングはその中にあって、顧客との強固な信頼関係を構築し、その価値が広く知られるようにすることだと考えます。
まず、マーケティングはお客さんを「徹底的に知る」ことが大事なんです。
そうです。恋愛でも同じですよね。
例えば、あなたが好きになった相手が「静かに本を読むのが好きな人」で、週末に図書館で過ごす時間を大切にしているとして、そのことを知っているのか、知らないのか?って、大きいでしょ?
どうしたらあなたを知ってもらえるのか?
相手に何を言えば関心をもってもらえるのか?
あなたの何に魅力を感じてもらえるのか?
あなたが本の苦手な人だったとしても、相手の暮らしを豊かに彩る存在になることができます。あなたは、相手にとって心地よい存在となり、大切な人になっていきます。
その中で信頼関係を育て、その信頼を裏切らないことであなたの良い印象は強固になっていきます。
それが「ブランディング」です。
この記事から読み取って頂きたいことは、単に「売れる」ことが大事なのではなく、顧客との関係をより素晴らしいものにしていくことが「事業を成長させる」と捉える感覚です。
そのために、真摯にマーケティングに取り組み、ブランディングを成功させることは企業にとって必要不可欠だということ…
です!
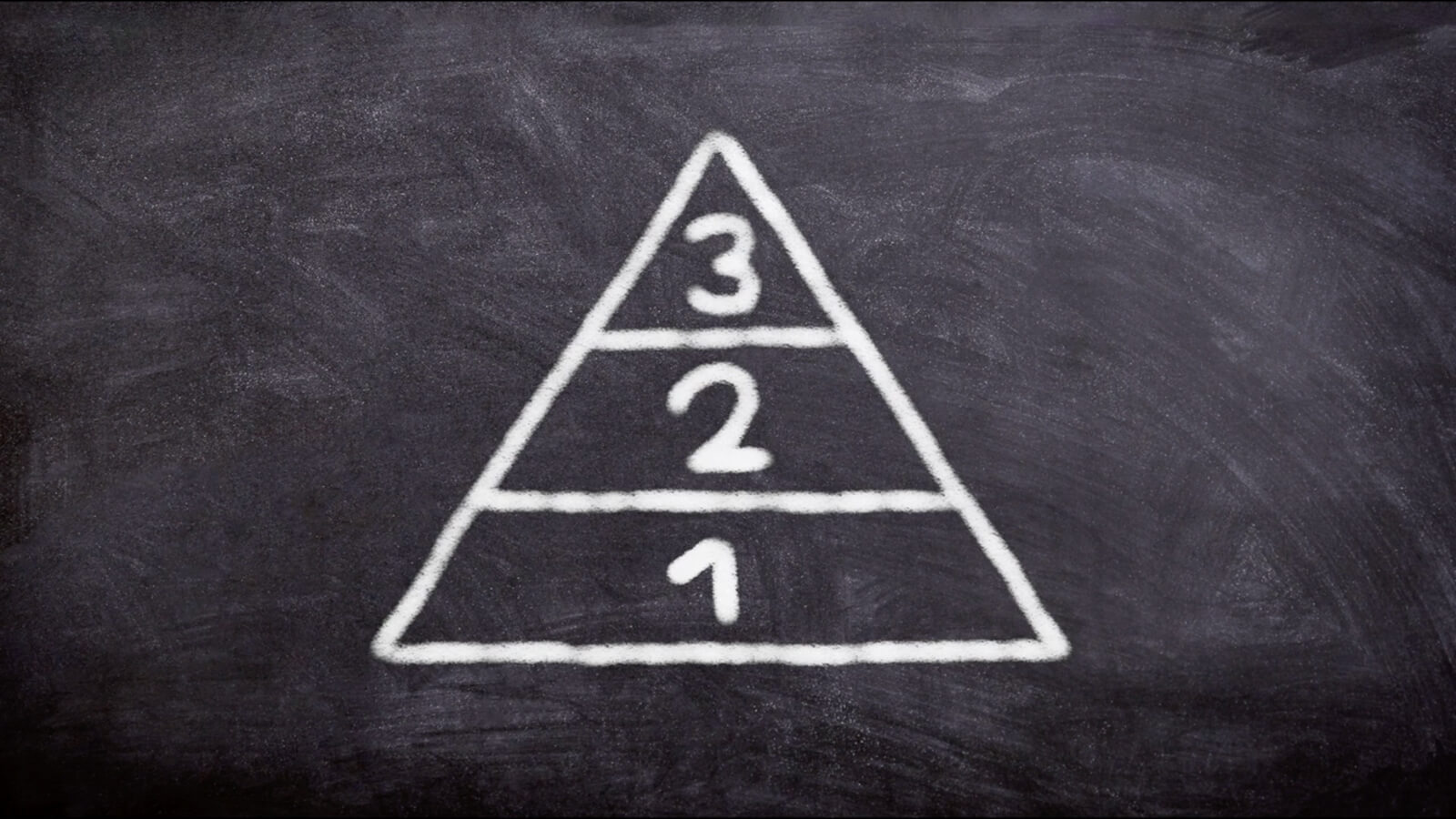
マーケティング・ブランディングが難しく感じる理由
さて、いざブランディングに取り組もうとすると、ネット記事を読みあさる、はたまたノウハウ本を買ってみるというケースが多いようです。資金を投じてコンサルさんにお願いするというのもありますね。
しかし、この巷に溢れる情報、私にはどうもしっくりこないんですよ…。
二等辺三角形を横に切った図形を前に「あれやって、これやって、ああしたらブランディングです」というように、知識は体系化され、深まっていきます。また、いろいろな事例から、ヒントがもらえるかもしれません。
ですが、抽象的な方法論や解説図を理解したとしても、何をして良いかが掴めず、積みあがった知識を具体的なアクションプランに落とし込めない企業さんは多いです。
画一的な知識の吸収が、あなたを部分的なアクションに終始させ、何がしたいのか分からない混乱を生んでしまい、ついにはブランディングどころか、蛇足だらけの奇妙な状況を生み出していたりするんです。
この蛇足ひとつ、ひとつに費用をかけていたりするとなると... 怖いですね!
「わかるけど、できない」
具体的な例としては「コンサルさんにお願いしてできたパンフレット」がブランディングとして正しいのか、そうでないのか?
「渡した文言は間違ってないし、それっぽくデザインされているので、これでいいかな」という話になるんですが、ブランディング的にNGということがよくあります。
(本物の)エルメスのバッグが街角でワゴンに乗って売られているなんてこと、ありえますか?
顧客の期待や憧れをズタズタにしてしまう路上という安価な商品の世界観、エルメスをコレクションしてきた人の満足感(ステータス、見栄など)を崩壊させてしまいますよね。
こんなことしたら、エルメスはそのブランドとしての歴史にピリオドを打つことになります。
あなたは「それは、おかしいに決まってる」と気付けると思うんです。
でも、あなたの会社、あなた自身について、会社の価値についてはどうですか?
ブランドの価値を正しく評価し、やってはいけないこと、やるべきことを判断していますか?
話が自分ごと、具体的になっていくと、学んだはずの知識が役に立たなかったりするんです。

大谷選手はブランディングのお手本
マーケティングには「向こうからお客がやってくる」「セールスを無用にする」といったお題がありますが、ブランディングには「企業としての在り方」が問われ、まだ顧客でない人たちにも好印象(イメージ)を育んでいく必要があります。
法人とはよく言ったもので、その企業の個性や根本が何なのかを問われるんです。
例えば、大谷翔平選手を見ていて、何よりも人を感動させる点は、その「人となり」だったりしませんか?
私たちが大谷選手に感動する理由を挙げると、身体能力や技術、実績と数えたらきりがありませんが、放たれるホームランを見るたびに、豪速球がストライクをカウントされるたびに、一途で爽やかな彼の「生き方」が染みて、胸が透くような感動に満たされていくのではないでしょうか?
手放しで応援したいと思わせる彼の生き方はブランディングのお手本だと言えます。
そうですね、彼の一貫した美学はぶれることがありません。
大谷選手の活躍に触れるたびに、彼のように真摯でいたいと思わせてしまう。
そんな彼の生き方への私たちの信頼は揺るがないものがありますね。
このように「内面をかためる」ことを、企業のブランディングでは「インナーブランディング」と呼びます。
また、社外、顧客や社会に企業や商品をアピールし、信頼関係を育てていく活動を「アウターブランディング」と言います。
目の前に落ちているゴミを拾う正しさや、仲間たち、そして世の中の人々の幸せのために、自らを律して頑張る「真摯な思い×行動」がとても大事だとわかると思います。
「社内のブランディング?分かるけど、それ、お金にはならなさそう」
「精神論?販売業や製造業の大変さに対する答えになってる?」
「大谷くんにはなれません!」
ええ、そうなんです。
資金を投じてインナーブランディングに取り組んだ企業さんもいますが、疑問があるとすれば「売上・利益・成長」を切り離したブランディングへの「これ、何になったんだ?」感だと思います。
企業全体における価値観、世界観を構築する。
これをお金(売上・利益)に変えてこそ、ブランディングができていると言えるんですね。
内(インナー)だ、外(アウター)だとか、なんだか複雑だと思われるでしょう?
本当にそうだと思います。

ブランディングツリーの発見
この難解なマーケティング、特にブランディングの理解を容易にし、実践的なものとするためのツールが「ブランディングツリー」です。
「あ、クリスマスツリー!」
「はい!そうです」
このクリスマスツリーを模したツールの中で、重要な要素は「土台」と「星」です。
ただし、ビジネスを成功へ導く決定的なことは「幹」の構築にあります。
いえいえ、商品やサービスをどうとらえて作り込んでいくか、オーナメントも超重要です。
え?全部じゃないか?
はい!そうです。全部重要です。
内側?外側?などなど、いろいろな要素がからみあった「ブランディング」の話...難解に感じたと思います。
次回、このブランディングツリーを使って、あなたに頭をスッキリさせていきます!
是非、続けてお読みください!
よくわかる!ブランディング
併せてoidcのYouTubeチャンネル【集客力を改善する、ブランディングの新解釈 "BRANDING TREE"】もご覧ください。
